~森と気象の関わり~
森林サービス分野
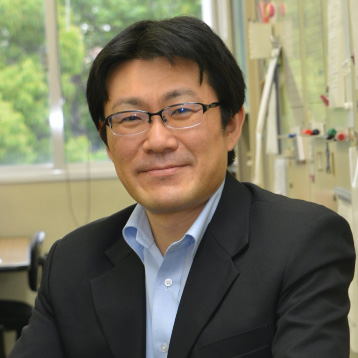
森林環境保全学研究室
小坂 泉(准教授)(Researchmap)
【主な担当科目】
森林環境保全学、森林気象学、森林基礎工学、森林環境保全学演習、森林気象学演習
【主な研究分野】
気候変動により森の息づかい( 森のCO2 吸収や放出) はどうなるのでしょうか?温暖化のダメージを受けると懸念されているブナが優占する演習林で研究しています。森全体をみる視点で森の働き( 例えば、炭素固定機能) を、実際の森で一緒に調べてみましょう!
〜研究テーマ①〜
ブナ林の長期モニタリング:気候変動と森の応答

・私たちは、ブナ林を対象として、気候変動が森林生態系に与える影響を長期的にモニタリングする研究を行っています。
特に、地球温暖化に伴う気温上昇や降水パターンの変化が、ブナの成長、光合成、水利用にどのような影響を及ぼしているかを詳細に分析しています。
具体的には、ブナ林の気温、湿度、日射、土壌水分などの気象要素を連続的に測定するとともに、ブナの葉のガス交換速度や気孔開度も測定して、気象条件が生理生態的な応答に及ぼす影響を解明しています。
その成果の1つとして、夏季の乾燥条件下で気孔の閉鎖が生じ、樹木の蒸散が抑制されることを観測データから明らかにしました。
これらの研究成果は、気候変動に対する森林生態系の脆弱性の評価に貢献するだけでなく、長期的なデータの蓄積を通じて、将来の気候変動予測モデルの精度向上にも寄与することが期待されます。
〜研究テーマ②〜
多雪地域における水循環と森林生態系の相互作用

・当研究室では、多雪地域における水循環と森林生態系の関係に着目しています。
多雪地域では、雪解け水が土壌水分や河川流量に大きな影響を与えるだけでなく、森林生態系の動態にも影響を及ぼします。
そこで本研究では、積雪量や融雪時期、土壌水分などの水文要素を測定し、さらに森林内の樹木の成長や蒸散量などを調査することで、水循環と生態系の相互作用を明らかにすることを目指しています。
近年の研究では、融雪時期の早期化が特定の樹木の成長や展葉開始のタイミングに影響を与えることが示されています。
これらの研究成果は、地球温暖化による積雪量の減少や融雪時期の変化が森林生態系に及ぼす影響を予測し、適切な森林管理を進める上での重要な知見となります。
また、多雪地域における水資源の持続的な管理にも貢献することが期待されます。
〜研究テーマ③〜
温暖地におけるブナの適応力

・近年、当研究室では、温暖な地域に植栽されたブナの生理生態と成長に関する研究を進めています。
ブナは本来、冷涼な気候を好む樹種ですが、地球温暖化の影響で生育適地が変化する可能性があります。
そこで本研究では、太平洋側の温暖な低地に植栽されたブナ成木を対象に、葉の光合成速度や蒸散速度を測定し、温暖な気象条件下における適応の実態を評価しています。
2023年に発表された論文では、温暖な地域に生育するブナは一定の光合成能力を維持し、冷温帯に生育するブナより水利用効率が高いことを報告しました。
また、冷温帯と暖温帯に植栽されたブナのガス交換特性および葉の形態的特徴を比較し、生育環境の違いが生理機能に与える影響を明らかにしました。
これらの研究成果は、将来的な地球温暖化の進行を踏まえ、ブナ林を維持するための適切な管理方法を検討する上で重要な情報となります。